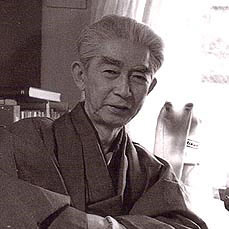
1946(昭和21)年に服部新佐博士によって設立された当研究所は、世界で唯一の蘚苔類(せんたいるい, =コケ植物)専門の研究機関です。在籍する専任兼任の十数名の研究員は、当研究所をはじめ、高知分室(高知県)など各地で蘚苔(せんたい)・地衣(ちい)類の研究を続けています。また、研究にともなう関連資料の収集・整理および研究成果の出版をしています。
約52万点の標本を所蔵し、国内外の研究者に貸出を行っています。

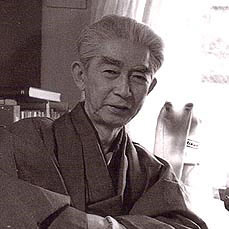
1946(昭和21)年に服部新佐博士によって設立された当研究所は、世界で唯一の蘚苔類(せんたいるい, =コケ植物)専門の研究機関です。在籍する専任兼任の十数名の研究員は、当研究所をはじめ、高知分室(高知県)など各地で蘚苔(せんたい)・地衣(ちい)類の研究を続けています。また、研究にともなう関連資料の収集・整理および研究成果の出版をしています。
約52万点の標本を所蔵し、国内外の研究者に貸出を行っています。

当研究所は日本及びアジアのコケ植物と地衣類の研究センターとして、研究活動を行っています。
令和3年3月31日現在、以下のような研究資料を所蔵しています。

令和4年3月31日までに蘚苔植物に関する以下の研究業績を刊行しました。
| 研究所名 | 公益財団法人 服部植物研究所(英語表記 Hattori Botanical Laboratory) |
|---|---|
| 住所 | 〒889-2535 宮崎県日南市飫肥6-1-26 |
| 設立 | 昭和21年3月15日 |
| 設立目的 | 植物特に蘚苔類を研究し、もって斯学の発展に寄与することを目的とする |
| 特色 | 世界で唯一の蘚苔類専門の研究機関である |
| 代表者 | 理事長 南壽 敏郎(Toshiro NASU) |
| 研究員 | 研究員 鄭 天雄(Tian-Xiong ZHENG)(理学博士) 吉村 庸(Isao YOSHIMURA)(理学博士)、その他非常勤研究員10名 |
| 鄭 天雄(常勤) Tian-Xiong ZHENG 博士(理学)(広島大学) |
平成4年生。服部植物研究所常勤研究員。標本管理責任者。 日本およびアジアのタイ類を中心に分類学的研究を進めており、特に蘚苔類の代表であるゼニゴケ科の分類に取り組んでいる。現在まで、ゼニゴケ科の分類に関する論文10余篇を発表。 |
|---|---|
| 吉村 庸(高知分室長) Isao YOSHIMURA 理学博士(東京教育大学) |
昭和8年生。元高知学園短期大学学長。元日本地衣学会会長。服部植物研究所高知分室長。 世界のヨロイゴケ科地衣類の権威。地衣類の分類のほか、含有成分の化学的な分析も精力的に行った。原色日本地衣類図鑑(保育社)のほか、現在までに地衣類の分類、生態、成分、生理に関する論文約180篇を発表。 |
| 湯澤 陽一(非常勤) Yohichi YUZAWA 理学博士(広島大学) |
昭和9年生。元福島県立平商業高等学校教諭。 これまで苔類ヤスデゴケ科の研究を続けてきた。東北地方の苔類に詳しく、自然保護にもつくしている。現在までに苔類の分類と分布の論文約50篇を発表。 |
| 長谷川 二郎(非常勤) Jiro HASEGAWA 理学博士(京都大学) |
昭和22年生。元南九州学園理事長。元日本蘚苔類学会会長。 植物の系統を研究する上で重要なツノゴケ類の研究を続け、多くの成果を挙げた。絶滅危惧蘚苔類の調査、保護に尽力している。現在までにツノゴケ類及び苔類の分類の論文約80篇を発表。 |
| 出口 博則(非常勤) Hironori DEGUCHI 理学博士(広島大学) |
昭和23年生。広島大学名誉教授。元日本蘚苔類学会会長。 日本及び世界の蘚類の分類学的研究を精力的に続けてきたが、特にギボウシゴケ科の研究では世界的に認められている。コケ植物の形態学的な研究も多い。現在までに蘚類の分類及び分布の論文を多数発表。 |
| 木口 博史(非常勤) Hiroshi KIGUCHI |
昭和30年生。元埼玉県立庄和高等学校教諭。 日本の石灰岩地の蘚類について研究した。またこれまで分類が困難であった蘚類のセンボンゴケ科の種について研究を続け、豊富な知識を得た。絶滅危惧蘚苔類の調査、保護に尽力している。現在までに蘚類の分類・生態に関する論文約60編を発表。 |
| 古木 達郎(非常勤) Tatsuwo FURUKI 理学博士(広島大学) |
昭和32年生。元千葉県立中央博物館研究部長。元日本蘚苔類学会会長。 日本及びアジアのコケ植物タイ類の分類学的研究を精力的に行なっている。特にスジゴケ科の研究では世界的に認められている。現在までにタイ類の分類や分布の論文を多数発表。また、日本産チェックリストや図鑑、レッドデータブックの執筆も行い、コケ植物の普及や保護・保全にも取り組んでいる。 |
| 山口 富美夫(非常勤) Tomio YAMAGUCHI 理学博士(広島大学) |
昭和34年生。広島大学大学院統合生命科学研究科教授。元日本蘚苔類学会会長。 琉球列島の蘚苔類の研究のほか、蘚類、特にシラガゴケ科、カタシロゴケ科の分類学的研究を行った。また、分子生物学的手法を使って、蘚類の系統を研究している。現在までに蘚苔類の分類・系統に関する論文約60篇を発表。 |
| 原田 浩(非常勤) Hiroshi HARADA 理学博士(広島大学) |
昭和35年生。千葉県立中央博物館植物学研究科主任上席研究員。日本地衣学会会報Lichenology編集委員長。 分類が困難であった痂状地衣のアナイボゴケ科などの研究など、分類学的研究を精力的に続けている。博物館においては多くの共同研究委員との共同研究を行うとともに、多数の市民研究員の指導を行っている。現在までに地衣類の分類に関する論文約140編を発表。 |
| 原 光二郎(非常勤) Kojiro HARA 博士(バイオサイエンス) |
昭和47年生。秋田県立大学生物資源科学部准教授。日本地衣学会会員。 服部植物研究所の地衣類研究に吉村庸研究員の共同研究者として参画。現在までに地衣類の分子系統解析、分子機構の解析および環境適応能力に関する論文7編を発表。 |
| 片桐 知之(非常勤) Tomoyuki KATAGIRI 博士(理学)(広島大学) |
昭和58年生。高知大学理工学部講師。2017~2021年までは研究所の三代目所長として活動。Hattoria編集長。 日本および東アジアのタイ類を中心に研究を進めており、特にムクムクゴケ科の分類学的研究では世界的に認められている。さらにコケ植物の化石を対象とした分類学的研究にも取り組んでおり、久慈産琥珀から新種のコケ植物を発見するなど白亜紀のコケ植物の多様性の解明などでも成果をあげている。現在までに蘚苔類の分類・系統に関する論文約60篇を発表。 |
| 井上 侑哉(非常勤) Yuya INOUE 博士(理学)(広島大学) |
平成元年生。国立科学博物館植物研究部研究員。 日本および東アジアの蘚類を中心に系統・分類学的研究を進めており、特に蘚類の大きな科の一つであるセンボンゴケ科の系統・分類に精力的に取り組んでいる。現在までに蘚苔類の分子系統、分類、フロラに関する論文約30篇を発表。 |
| 昭和21年(1946) 3月15日 | 杉造林地及び銀行預金を基本財産として服部新佐(初代理事長兼所長)が財団法人服部植物研究所を設立. |
|---|---|
| 昭和22年(1947) 4月19日 | 財団法人服部植物研究所報告第1号を発行.服部植物研究所報告の発行は内外の多くの研究者に論文発表の場を提供し、特に多くの学位論文を掲載して、有能な研究者の育成に寄与し、日本の蘚苔類学を欧米の水準に引き上げた. |
| 昭和23年(1948) 4月 | 文部省民間学術研究機関補助金の交付を受けた.これ以降、毎年交付を受けるようになり研究所の内容が充実する. |
| 昭和29年(1954)10月 4日 | 服部植物研究所報告第11号に初めて外国人研究者の論文を掲載。以後ほとんど総て英文となる. |
| 昭和33年(1958) 9月19日 | 服部植物研究所報告第20号発行頁数が300以上となる.この頃から米仏の学会誌とともに世界の蘚苔類の四大専門誌と評価される. |
| 昭和39年(1964) 11月 3日 | 服部植物研究所(団体)が西日本文化賞を受賞 | 昭和45年(1970)11月10日 | 服部新佐理事長紫綬褒章受章 | 昭和46年(1971) 5月 | 研究所創立25周年記念行事として国立科学博物館でコケ展を開催 |
| 昭和46年(1971) 5月18日 | 日米蘚苔類セミナーを東京で開催(国立科学博物館、米国16名、日本8名、日米科学協力事業) |
| 昭和51年(1976) 4月12日 | 岩月善之助所長就任 |
| 昭和52年(1977) 1月19日 | 服部新佐理事長朝日賞受賞 |
| 昭和58年(1983) 5月23日 | 服部植物研究所を中心に国際蘚苔類学会を開催.この会議に出席した外国の研究者約30名を日南に招いた. |
| 昭和59年(1984) 1月 1日 | 岩月善之助所長広島大学に転出 |
| 平成 4年(1992) 5月12日 | 初代理事長服部新佐死去 |
| 平成 4年(1992) 5月30日 | 杉田禮子理事長就任 |
| 平成 5年(1993) 3月31日 | 岩月善之助所長広島大学定年退職 |
| 平成 5年(1993) 4月 1日 | 愛知県岡崎市に岡崎分室を設立 |
| 平成14年(2002) 8月 1日 | 高知県伊野町に高知分室を設立 |
| 平成19年(2007) 5月18日 | 南壽敏郎理事長就任 |
| 平成22年(2010) 2月 6日 | 岩月善之助所長松下幸之助花の万博記念賞を受賞 |
| 平成22年(2010) 4月 1日 | 静岡県島田市に島田分室を設立 |
| 平成23年(2011) 9月 1日 | 常設展示場を日南市飫肥に開館 |
| 平成25年(2013)10月 1日 | 公益財団法人に移行 |
| 平成27年(2015)11月29日 | 服部新佐博士生誕100年記念講演会を開催 |
| 平成27年(2015) 9月15日 | 岩月善之助所長死去 |
| 平成28年(2016)11月27日 | 服部植物研究所創立70周年記念講演会を開催 |
| 平成29年(2017) 3月31日 | 岡崎分室(愛知県岡崎市)を廃止 |
| 平成29年(2017) 4月 1日 | 片桐知之所長就任 | 平成30年(2018) 11月 5日 | 服部植物研究所(団体)が宮崎県文化賞(学術部門)を受賞 | 平成31年(2019) 3月 8日 | 井上侑哉研究員が日本植物分類学会奨励賞を受賞 | 平成31年(2019) 3月 29日 | 服部植物研究所が国登録有形文化財(建造物)に登録 | 令和元年(2019) 9月 10日 | 鈴木直研究員死去 | 令和2年(2020) 3月 31日 | 島田分室(静岡県島田市)を廃止 | 令和2年(2020) 8月 30日 | 水谷正美博士死去 | 令和3年(2021) 9月3-4日 | 日本蘚苔類学会第50回記念宮崎大会(オンライン大会)(主催:日本蘚苔類学会, 共催:服部植物研究所)を開催 | 令和3年(2021) 9月 4日 | 服部植物研究所(団体)が日本蘚苔類学会特別賞を受賞 | 令和3年(2021) 9月 19日 | 服部植物研究所(団体)が日本植物学会賞特別賞を受賞 | 令和3年(2021) 12月 1日 | 片桐知之所長高知大学に転出 | 令和4年(2022) 2月 5日 | 服部植物研究所(団体)が松下幸之助花の万博記念賞<松下正治記念賞>を受賞 | 令和4年(2022) 4月 1日 | 鄭天雄博士 常勤研究員着任 | 令和4年(2022) 10月31日 | 服部植物研究所研究・標本棟が国登録有形文化財(建造物)に登録 | 令和5年(2023) 1月 11日 | 山田耕作博士死去 | 令和5年(2023) 4月 1日 | 鄭天雄博士 標本管理責任者就任 |